
|
枚数にかかわらず鉛電池固有のものです。
取り出すことができる(蓄えることができる)電気の量は極板の鉛の量に比例するため、通常は数枚の陽極板・陰極板と陽極板・陰極板の短絡を防止するためのセパレータ(隔離板)などで構成されていて、これを極板群といい、電池の最小単位としてセルに納められています。このセルを6組直列に接続すると12Vのバッテリになり12組直列に接続すると24Vのバッテリになります。大容量のバッテリでは極板が大きく、極板の枚数も多くなっています。
(2)電槽とふた
電槽とは、極板群や電解液を入れるための容器で、合成樹脂で作られています。内部は単電池(セル)数に応じ隔壁で分割されています。ふたは電解液が外部に飛び散るのを防止するためのもので、電槽の上部に接着されています。
(3)液口栓
ふたには希硫酸や精製水を注入するためと、電解液の比重や温度を計測するための液口があります。液口には電解液が外にこぼれないよう、また、外部からゴミが入らないように液口栓が設けられています。液口栓の中央または側部に小さい孔(排気口)があってバッテリの内部から発生する水素ガスや酸素ガスを外部へ放出し、硫酸霧はバッテリ内部に還流する構造になっています。
(4)端子
各セルは鉛合金の接続カンで直列に接続され、両端のセルには外部のケーブルと接続するための端子があります。端子は一方が+端子、他方が−端子になっています。
(5)電解液
電解液は、純度の高い硫酸と、純粋な水を混合して作られた希硫酸で、陽極板と陰極板との化学反応で起電力を発生します。完全に充電された状態の電解液の比重は1,280(20℃)で、その時の電解液の硫酸の濃度は約37.5%です。
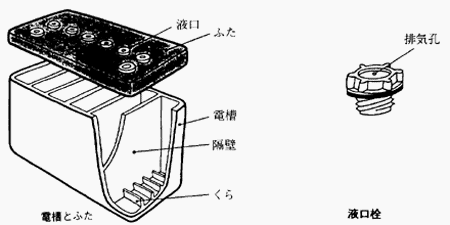
前ページ 目次へ 次ページ
|

|